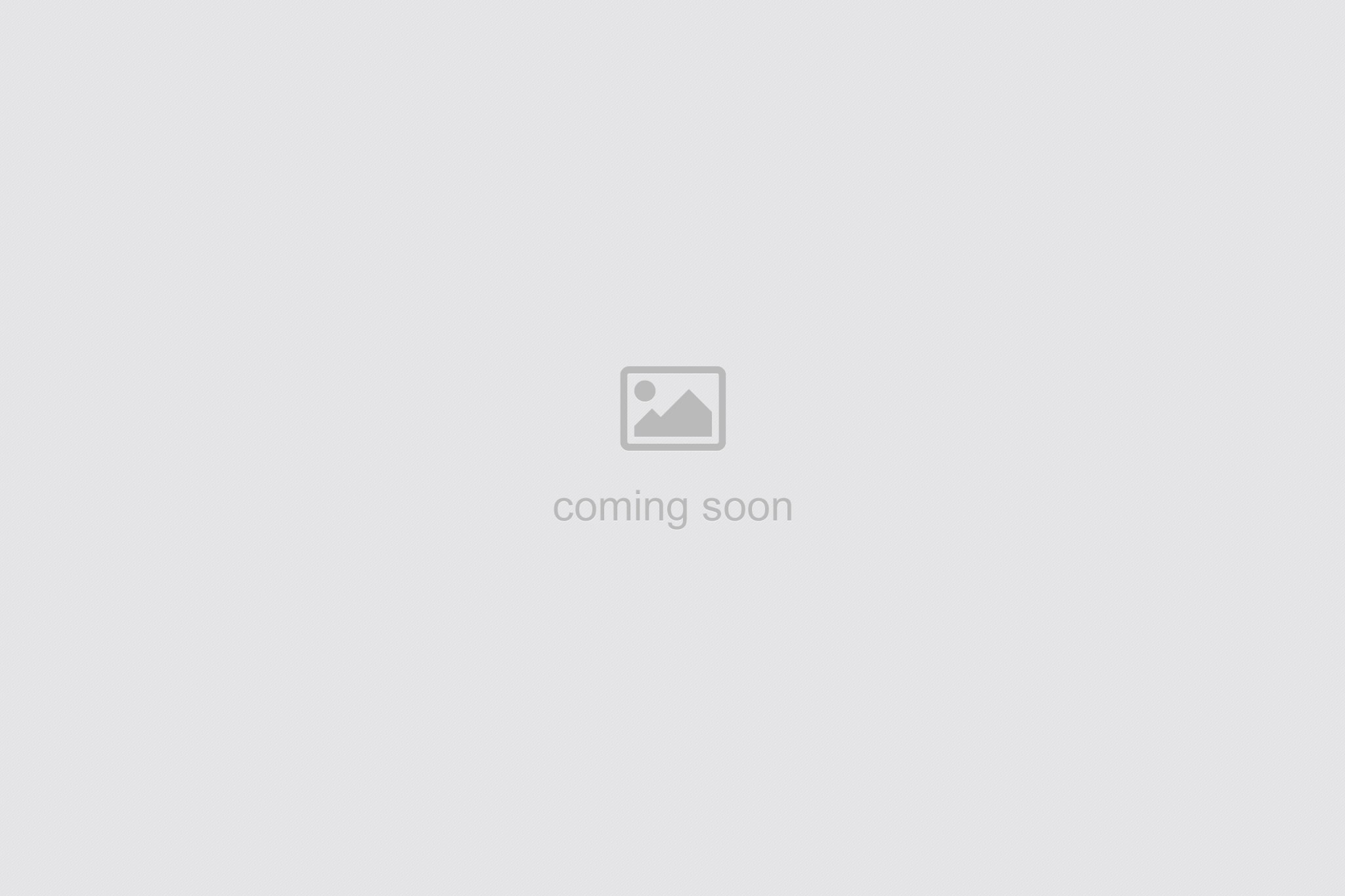園内研修
2024年度
避難訓練について
6月は、避難訓練についての研修 地震・火災・不審者・二次避難の職員の動きについて、細かく確認・共通理解しました
地震・火災・不審者・二次避難の職員の動きについて、細かく確認・共通理解しました
二次避難時の非常持ち出し物の内容についても確認したので、避難後の生活にも備えておければと思います
毎月様々な想定で行っている訓練ですが、いざという時に各自が咄嗟に責任をもって安全に動けるように取り組んでいきたいと思います
マーチング
5月は、マーチングの研修
「初級者コース」では、子どもたちに指導したことのない職員が対象となり、足ぶみ・方向変換・手やバチを使ったリズムうちなど、基本的なことを学びました 1年を通して、日々の練習に参加しながら指導法などを少しずつ身につけていきたいと思います
1年を通して、日々の練習に参加しながら指導法などを少しずつ身につけていきたいと思います
次に、「楽器指導者コース」として、楽譜の読み方・各楽器の演奏法・実際に演奏してみるなど、今年度指導する職員を対象に行いました
今年度もみんなで協力しながら、子どもたちが堂々と発表できるように指導していきたいと思います